みなさんこんにちは、らくとです。
みなさん、突然ですが、小説において、作者のセンスが問われる部分ってどこだと思いますか?
もちろん、メインは文章やストーリーです。でも、それらよりも早く、真っ先に私たちの目に入るもの。いわば、私たちが読むその物語の、本当に、最初の一言目、第一声ともいえる・・・
そう、「タイトル」です。
タイトルというのは、本の第一印象を決めるとても大切なもの。また、何百ページにもわたる物語をたった一言 で的確に表し、しかも読者にインパクトや好印象まで与えることまで求められるという点で、かなりのセンスが問われます。
では、いいタイトルとはどういうものなのでしょうか。前置きとして個人論を少しだけ話しておきたいと思います。
- いいタイトルとは?
- 秀逸なタイトルの本23選!
- 一瞬の風になれ:佐藤多佳子
- 夏と花火と私の死体:乙一
- 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない:桜庭一樹
- 宵山万華鏡:森見登美彦
- アヒルと鴨のコインロッカー:伊坂幸太郎
- すべてがFになる:森博嗣
- 君の膵臓をたべたい:住野よる
- 夏への扉:ハインライン
- ベルカ、吠えないのか?:古川日出男
- アルジャーノンに花束を:ダニエル・キイス
- きょうの日はさようなら:一穂ミチ
- その可能性はすでに考えた:井上真偽
- 豆の上で眠る:湊かなえ
- ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー:ブレイディみかこ
- 自転しながら公転する:山本文緒
- クラインの壺:岡嶋二人
- 正欲:朝井リョウ
- 世界でいちばん透きとおった物語:杉井光
- 同志少女よ、敵を撃て:逢坂冬馬
- 新世界より:貴志祐介
- 舟を編む:三浦しをん
- 奇想、天を動かす:島田荘司
- 人間失格:太宰治
- まとめ
いいタイトルとは?
では、いいタイトルとは具体的にはどういったタイトルなのでしょうか?これは好みの問題なので、一概には言えませんが、ここでは私の個人的な考えを軽く説明します。
まず大前提として、「内容としっかり繋がりがある」ということが大切です。
つまりは、その小説の内容や、伝えたいことを的確に表しているかということです。いくらかっこよかったり洒落たりしていても、内容とあまり関係がなかったり、あったとしても薄い繋がりだったりしたら、いいタイトルとは私は思いません。
私が個人的に好きなのが、一見するとそこまでインパクトがあるわけでもない、一般的な言葉の組み合わせだったり、たった一単語のシンプルなタイトルであっても、小説を読み終わったあとにタイトルに戻ってみると、「ああ、だからこのタイトルなのか」と深く納得できるようなものです。全てを読み終わってはじめて、真の意味が分かるような、普通の言葉が違った意味を帯びてくるようなタイトルは、いいなあ、と思います。
そして、更に、+αとして、「インパクト・好印象を与える」ことができればより完璧だと思います。では、どんなタイトルだとインパクト・好印象を与えられるかというと、それははっきりとした答えがあるわけではなく、本当に様々です。その中から例をいくつかあげてみると、まずは、「読者に疑問を持たせるようなタイトル」です。「これってどういう意味だろう?」「なんでこんなタイトルにしたんだろう?」・・・見た人がそんな風に思うタイトルはインパクトがあり、思わず本を手に取ってしまいます。また、個人的に、「命令形や疑問形のタイトル」や、「文章が途中で途切れているようなタイトル」もどことなくかっこよくて、好きです。
(ちなみに私自身としては、タイトルとかキャッチコピーとか見出しとか、そういう短いけれど適切でかつ印象的なフレーズというのを考えるのが苦手なタイプなので、こういうセンスのある人、素直にすごいなーと思います。)
秀逸なタイトルの本23選!
では早速、私が個人的に「秀逸だな」「センスがいいな」と思うタイトルの小説を23冊、紹介していきたいと思います。
一瞬の風になれ:佐藤多佳子
まずは、佐藤多佳子さんの青春小説、「一瞬の風になれ」です。(全部で3巻ありますが、リンクは1巻のみ貼っておきます)
陸上に全てを捧げる高校生たちの情熱を描いた、青春小説の傑作です。
走ることを「風になる」と表現するセンスはもちろんですが、どれだけ練習を積んでも、時間をかけても、陸上の短距離のレースの時間はとても短く、その数秒の中に青春の全てが詰まっていることを表す「一瞬の」という言葉がとてもいいな、と思います。爽快感と情熱を同時に感じるタイトルです。
夏と花火と私の死体:乙一
次は、乙一さんのホラー小説、「夏と花火と私の死体」です。
これは誤って同級生を殺してしまった小学生が、死体を隠すために奮闘する夏の数日間を描いたホラー小説です。当時まだ16歳だった乙一さんの、才能を感じさせるデビュー作です。
このタイトルはやはり、前半と後半のアンバランスさが印象的ですよね。「夏と花火と」までは、順調に爽やかな夏の風景が浮かぶのに、その直後に突然来る「私の死体」という不穏すぎる言葉。これが、読者に「え?」と思わせ、興味を引きます。そして、その不気味なアンバランスさは、タイトルだけではなく、作品全体にも漂っています。そして、さらに注目すべきは、「私の死体」という言葉。よく考えたらおかしな言葉だと思いませんか?
なんとも薄気味の悪いこの作品(褒めてます)にぴったりなタイトルだと思います。
砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない:桜庭一樹
次は、桜庭一樹さんの青春小説(?)、「砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない」です。
二人の少女の、「子どもである」という絶望的な現実との戦いを描いた青春小説の傑作です。ただ、これを青春といっていいものかは個人的には疑問です。カテゴライズすることの難しい、独特な作品だと思います。
この少し長めのタイトルは、おそらく、未読の人には意味が分からないと思います。けれど、この物語を全て読むと、この作品にこれ以上のタイトルはない、と思うはずです。とても独特で、でも的確で、かつお洒落な桜庭さんの比喩表現のセンスが遺憾なく発揮された、唯一無二のタイトルです。
宵山万華鏡:森見登美彦
次に紹介するのは、森見登美彦さんのファンタジー小説、「宵山万華鏡」です。
京都の祇園祭宵山のある一日、祭りを楽しむ人混みの中で、人知れず起こっているちょっぴり怖くて不思議な出来事たちを描いたファンタジー小説です。個人的に大好きな作品です。
「宵山万華鏡」というタイトルは一見シンプルですが、この作品の雰囲気にベストマッチのタイトルだなあ、と思います。お祭りの華やかさ、浴衣や露店などで溢れかえる鮮やかな色彩、その中で起こるめくるめくような不思議な出来事の数々・・・この物語は、ちょっと筒を回す度に、色とりどりの様々な柄が次々と現れる万華鏡によく似ています。万華鏡を覗くようなわくわくを味わえる一冊です。
アヒルと鴨のコインロッカー:伊坂幸太郎
次に紹介するのは、伊坂幸太郎さんのミステリー小説、「アヒルと鴨のコインロッカー」です。
隣人からの「一緒に本屋を襲わないか?」という突然の誘いから始まった、ある大学生のおかしな日々を描くミステリー小説です。文体は軽快ですが、どことない切なさも漂う名作です。
こちらも一見すると全く意味の分からないタイトルですよね。「アヒル」と「鴨」は分かるとしても、そこにコインロッカーって・・・?とみんな?を浮かべると思います。けれども、実はこれも読み終えた後にじんわりと余韻が来るタイプのタイトル。伊坂幸太郎さんも比喩表現や文体にかなり特徴のある作家さんで、わりと重めのことでも、できるだけドライに、軽く表現しようとするイメージですが、そこには確かに温かさがあります。このタイトルも、すごく伊坂さんらしいな、と思います。
すべてがFになる:森博嗣
次に紹介するのは、森博嗣さんの本格ミステリー、「すべてがFになる」です。
孤島にある天才工学博士の研究所で起きた奇妙な密室殺人の謎に大学助教授が挑む、本格ミステリー小説です。S&Mシリーズの1冊目としてミステリー界でもかなり有名で、森博嗣さんのデビュー作でもあります。
このタイトルも、一見意味分からない系ですよね。この言葉の真の意味は作中で明らかになるのですが、そのときの感動はちょっと忘れがたいです。なんか自分の理解の遠く及ばないものを前にして恐ろしいと思うと同時に美しいとも思うような、そんな感じでした。ただ、その種明かしより前にこのタイトルの意味を看破できる人は、常人ではいないと思います。難解だけれど美しい作品です。
君の膵臓をたべたい:住野よる
次に紹介するのは、住野よるさんの「君の膵臓をたべたい」です。
病気で余命僅かな少女と、それを偶然知ってしまったクラスメイトの少年の交流の日々を描いた小説です。若い世代を中心に大ヒットし、普段本を読まない人にまで読まれた大ベストセラーです。
なんといっても、やはり真っ先に目が行くのは、強烈なインパクトを残すこのタイトル。タイトルだけみると、何だかホラー小説のようですよね。でも、表紙は桜を背景にした制服の男女といかにも青春小説っぽい。この表紙とタイトルのギャップにひかれて興味を持った人も多いのではないでしょうか。あらすじを見ても、やっぱり感動ものの青春小説っぽいし、じゃあ、このタイトルはどういう意味で付けられたんだろう・・・?気になってしまいますよね。そして、このタイトルは、インパクトを与えるためだけの言葉ではなく、大切な意味が込められていることが、読み終わったときにはよく分かります。
夏への扉:ハインライン
次に紹介するのは、ハインラインの「夏への扉」です。
恋人と友人に裏切られた上、命の次に大切なものまで奪われてどん底にいた主人公が、「冷凍睡眠(コールド・スリープ)」を使って、自身の幸せを取り戻そうと奮闘する様を描いた、SF小説の傑作です。個人的に大好きな作品です。
「ぼくの飼っている猫のピートは、冬になると決まって夏への扉を探しはじめる」――あらすじに書かれている有名なフレーズです。凍えるほど寒い冬でも、たくさんある家の扉のどれかが夏に続いていると信じて、ドアを一つ一つ開いて夏を探し続ける・・・これは主人公の飼い猫・ピートの話です。そして、主人公自身もまた、人生の冬の真っ只中にいます。大切なものをほとんど失ってしまった主人公は、しかし、そこで諦めることをせず、ときには危険に身をさらし、ときには自身の運に賭けながら、自分自身が幸せになる道を探し続けるのです。その姿は、夏への扉を求めてドアを開け続けるピートの姿に重なります。この扉の先が夏かどうかは、開けてみないと分からない・・・個人的に、このシンプルだけれど前向きなメッセージが込められたタイトルは、この作品にぴったりだと思います。
ベルカ、吠えないのか?:古川日出男
次に紹介するのは、古川日出男さんのエンターテイメント小説、「ベルカ、吠えないのか?」です。
キスカ島に残された4頭の軍用犬を始祖とするイヌたち。国境も海峡も思想も越えて、20世紀という戦争の時代を駆け抜けた彼らの長い歴史を描いた、凄まじい熱を感じる小説です。
今の日本では、私たちが目にして接するイヌは、ペットとして家庭で飼われている子がほとんどで、人懐っこくて可愛いイメージが強いと思います。けれど、イヌというのも、元は獣であり、本気になれば人間だって殺せるだけの力と牙を持っているのです。この小説の主人公は、軍用犬。人間に利用され、振り回される存在ではありつつも、獣としての鋭さや激しさ、そして矜持も持っている彼らの姿が、本書ではスピード感と熱量凄まじく描かれています。そして、彼らに呼びかけるような、誇りを思い出させるようなこのタイトルは、この荒々しく勇猛な物語にぴったりです。
アルジャーノンに花束を:ダニエル・キイス
次に紹介するのは、ダニエル・キイスの名作、「アルジャーノンに花束を」です。
32歳だが幼児なみの知能しかないチャーリイ。しかし、彼は、ある大学の先生の手術により奇跡的に知能を向上させます。天才になった彼が知った、人の心の真実とは?・・・世界的にも有名で、涙なしには読めない不朽の名作です。
これは数年前に初めて読んだのですが、本当の本当に名作だと思います。心を大きく揺さぶられて、読後もしばらくこの作品について、チャーリイについて、考えずにはいられなくなるような、そんな作品でした。このタイトルにある「アルジャーノン」というのは、チャーリイが受けた手術の効果を調べるための実験動物である白ネズミの名前です。このタイトルの意味が分かるのは本当に最後なのですが、個人的に、タイトルの伏線回収がすごく美しく、深い余韻を残す作品だと思いました。
きょうの日はさようなら:一穂ミチ
次に紹介するのは、一穂ミチさんの青春小説、「きょうの日はさようなら」です。
双子の高校生が、三十年という長い眠りから目覚めたばかりの女子高生と過ごしたひと夏を描いた、切なさ残る青春小説です。作者は最近人気の上がってきた作家・一穂ミチさんです。
1995年から時が止まったままの女子高生が、2025年に目覚めてひと夏を過ごすという話です。明るいような寂しいような夏の雰囲気とストーリーが相まって、全体的に切ない一冊となっています。けれども、この「きょうの日はさようなら」というタイトルには、その切なさに負けない希望が込められています。楽観的で、でもその分まっすぐなその希望は、読後もしばらく深い余韻を残します。
その可能性はすでに考えた:井上真偽
次に紹介するのは、井上真偽さんの本格ミステリー、「その可能性はすでに考えた」です。
山村で起きたカルト宗教団体の斬首集団自殺。唯一生き残った少女の不可解な記憶の真偽とは。探偵・上苙丞はその謎が奇蹟であることを証明できるのか?新しすぎる本格ミステリー。
「トリックを推理をしてたった一つの真相を解き明かす」のが、これまでの普通のミステリーでした。けれどこの作品は、発想の転換により、大胆にその常識を覆してみせた、まさに新しすぎる本格ミステリーです。タイトルにもなっている「その可能性はすでに考えた」というのは、この作品に出てくる探偵の決め台詞なのですが、ここでもうっすら分かるように、この探偵は、推理するのではなく、推理を「否定する」探偵なのです。どういうこと?と思った人はぜひ、実際に手に取ってみてください。
豆の上で眠る:湊かなえ
次に紹介するのは、湊かなえさんのミステリー、「豆の上で眠る」です。
一度失踪して、二年後に帰ってきた姉。月日が経っても、私だけが拭えない違和感を抱き続けている。お姉ちゃん、あなたは本物なの?衝撃の姉妹ミステリー。
こちら、正直、どういう意味なのか読むまでは全く分からなかったのですが、意味が分かったときに、「上手に表現するなあ・・・」と感心してしまったタイトルです。失踪から帰ってきた姉が本物かどうか疑い続けている妹の話ですが、ずっと感じ続けている家族ならでの些細な違和感、そして、その正体を確かめずにはいられない気持ちを、「豆の上で眠る」という比喩によって、的確に表現しています。
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー:ブレイディみかこ
次に紹介するのは、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」です。
人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼくは、パンクな母ちゃんとともに、悩みながらも毎日を乗り越えていく。世界の縮図のような英国の学校の実情と、その中で育まれる友情と少年の成長を描いたリアルストーリー。
こちらは、ブレイディみかこさんが自身の息子さんを主人公にして描いた、ノンフィクションに近い小説となっています。イギリスの学校は、ほぼ単一民族の日本とは違い、国籍や人種が違う子どもが一緒に通っていて、貧富の差などもわりとはっきりしています。もちろん差別などの問題も絶えませんが、子どものうちから多様性を学び、受け入れるにはよい環境と言えるでしょう。この作品のタイトルは、白人であるイギリス人と黄色人種である日本人のハーフである「ぼく」自身、そして、様々な問題に直面し、塞ぎ込みがちな「ぼく」の気持ちを表しています。一人の人間の中に様々な色があるという多様性の意味も含まれており、また印象にも残る良タイトルだと思います。
自転しながら公転する:山本文緒
次に紹介するのは、山本文緒さんの「自転しながら公転する」です。
東京から戻って地元のモールで働き始めた32歳の都。恋愛、結婚、仕事、親の介護・・・全部完璧にやるなんて、無理!頑張る人たちに温かなエールを送る、共感度100%小説。
「自転しながら公転する」・・・この言葉を見たときに、まさに人生のことを表しているようで、はっとしました。恋愛や結婚、親の介護など、自分自身の人生のこともしっかり考えて上手くやりくりしながら、仕事もちゃんとして、社会のために働かないといけない。しんどくても、止まってしまえばあっという間に置いて行かれる世界では、止まるわけにはいかない。そんなしんどさが伝わってきて、でも同時に、そんなに大変なんだから、上手く行かないことがあって当たり前、悩んで焦って、失敗したって当たり前、とも思えて元気がもらえました。20代後半から30代前半くらいの女性に特に読んでほしい作品だと思います。
クラインの壺:岡嶋二人
次に紹介するのは、岡嶋二人さんの「クラインの壺」です。
ゲームブックの原作を謎の企業に200万円で売却した上杉は、その原作を元にしたヴァーチャルリアリティ・システム『クライン2』の制作に関わることになるが・・・。名作ミステリ。
タイトルとなっている「クラインの壺」というのは、位相幾何学で主に使われる、実在する言葉です。いわゆる「メビウスの帯」と似たようなものと思ってもらえたらいいでしょう。そしてこの作品は、限りなく現実に近い仮想現実に入り込んでゲームができるという、そんな夢のようなゲーム機『クライン2』の開発に関わるミステリー小説です。その近未来的設定ですでに面白いのですが、この作品が真価を発揮するのは、まさにこのタイトルの意味が分かるその瞬間。その衝撃は、ちょっと今までにはないものでした。ぜひ読んでみてください。
正欲:朝井リョウ
次に紹介するのは、朝井リョウさんの「正欲」です。
息子が不登校になった検事。初めての恋に気付く女子大生。一つの秘密を抱える契約社員。ある事故死をきっかけにそれぞれの人生が重なり始める。読む前の自分には戻れない、気迫の小説。
人間の三大欲求としてあげられるのは、食欲・睡眠欲・性欲の三つですよね。それ以外にも人間には様々な欲があります。その中でも、誰もが当たり前に持っているのに、持っていることすら意識されないものに、「正しくありたい」という欲があると思います。正しくありたい欲、それはときに、「多数派でありたい欲」というのにすり替えられることもあります。正しい、というのはどういうことで、そして、誰がそれを決めるのか。「多様性」という言葉が声高に、そして至る所で叫ばれるこの時代、多様生というのは一体何で、それを尊重するというのはどういうことなのか、改めて考える機会をくれる一冊だと思います。
世界でいちばん透きとおった物語:杉井光
次に紹介するのは、杉井光さんの「世界でいちばん透きとおった物語」です。
死去した大御所ミステリ作家・宮内彰吾の愛人の子どもである僕。宮内の長男からの連絡をきっかけに始まった遺稿探しは、予測不能の結末を迎える・・・。前代未聞、衝撃のミステリー。
すごく話題になっていたミステリー小説です。とてもロマンチックで詩的なタイトルですが、その本当の意味を読む前から予測できる人はきっといないでしょう。「世界でいちばん透きとおった物語」とはどういう物語なのか・・・それが明らかになったとき、鳥肌が立つほどの衝撃を受けました。ミステリー界のみならず、出版界全体に、全く新しい形の小説の楽しみ方・面白さを示してくれた作品だと思います。
同志少女よ、敵を撃て:逢坂冬馬
次に紹介するのは、逢坂冬馬さんの「同志少女よ、敵を撃て」です。
モスクワ近郊の村に住んでいたセラフィマは、家族や村人をドイツ軍によって殺され、赤軍にその死体を燃やされる。復讐を胸に誓い、訓練学校に入学し、女性狙撃兵となった彼女は、いくつもの激戦を戦い抜いていくが・・・。
こちらも、ロシア・ウクライナ戦争開始などの国際情勢も相まって、日本でかなり話題になった作品です。独ソ戦で暗躍した女性狙撃兵たちの話です。憎しみを胸に抱えて、敵に冷酷に狙いを定め、引き金を引いていく少女たちの姿は、戦争の哀しさ、恐ろしさを私たちに伝えてくれます。でも個人的に私が一番しびれたのは、タイトルの意味が分かった瞬間でした。彼女にとっての本当の「敵」とはいったい誰なのか・・・こんな意味も込められていたんだな、と感嘆したタイトルでした。
新世界より:貴志祐介
次に紹介するのは、貴志祐介さんの「新世界より」です。(上中下とありますが、リンクは上のみ貼っておきます。)
1000年後の日本。「神の力(念動力)」を得るに至った人類が手にした平和。子どもたちは野心と希望に燃えていた・・・隠された先史文明の一端を知るまでは。SFの傑作。
上・中・下と文庫にして3巻からなる、長く深い物語です。舞台は日本ですが、時代は今から1000年後。人類は超能力を手にし、生息する生き物や文化なども今とはかなり違います。そこは日本だけど日本じゃない、まさに「新世界」。そんな「新世界」から、この物語は、今の時代の私たちに何を伝えたがっているのでしょうか。この「新世界より」というタイトルは、もちろんドヴォルザークのクラシック曲が由来で、作中にも流れる場面があるのですが、そこが私の中ですごく印象に残っています。そして、このあまりにも壮大な物語にどんなタイトルをつけるかというのはかなりの悩みどころだと思うのですが、あえてたった5文字の「新世界より」というシンプルなタイトルをつけた作者の潔さが個人的に素晴らしいと思いました。
舟を編む:三浦しをん
次に紹介するのは、三浦しをんさんの「舟を編む」です。
出版社で働く馬締光也は、言葉への鋭いセンスを買われ、新しい辞書『大渡海』の完成に向けて進む辞書編集部へ引き抜かれた。不器用な人々の思いが胸を打つお仕事小説。
紙の辞書作りという、はっきりいうとマイナーな仕事にスポットを当てた作品です。日本にある全ての言葉を網羅し、時代とともに生まれる言葉も付け加え・・・一つの辞書を一から作るというのは、途方もなく地道な作業です。一つ一つじれったくなるような細かい工程を繰り返しながら、一つの大きなものを作りあげる・・・それはまさに「編む」という表現がぴったり。そして、辞書を「言葉の海を渡る舟」と表現しているところにも、辞書に対する情熱が感じられてぐっと来ます。読むと、もっと自分の周りにある言葉を大切にしたくなる、そんな本です。
奇想、天を動かす:島田荘司
次に紹介するのは、島田荘司さんの「奇想、天を動かす」です。
浮浪者風の老人が、浅草で、消費税12円のために店の主婦をナイフで刺殺した。老人は氏名すら名乗らず黙秘を続けている。この事件の裏には一体何が?島田荘司の隠れた名作。
このタイトルが好きなのは、響きがかっこいいというのもありますが、一番大きな理由として、島田荘司さんのミステリ作家としての素晴らしさを簡潔に表した言葉だな、と思うからです。島田荘司さんのミステリ作品って、「現実にはあり得ないような出来事を、壮大なトリックを使って現実の出来事として説明を付ける」という作品が多く、それがとても優れていると思うのですが、それを言葉で表現すると、まさに「奇想、天を動かす」。あっと驚くような発想とトリックで、見えていた世界をがらりと変えてしまう、そんな「奇想天外」と「驚天動地」を掛け合わせたようなこの言葉は、島田荘司さんにぴったり。現にこの作品でも、夜の列車の中でピエロが消失したり、死体が起き上がったり、挙げ句雪の中に巨大な白い巨人が出現したりと、奇々怪々な出来事が次々と起こります。どんな「奇想」でそれらに説明を付けるのか、ぜひ読んでみてください。
人間失格:太宰治
次に紹介するのは、太宰治の「人間失格」です。
3枚の奇怪な写真とともに渡された睡眠薬中毒者の手記には、その陰惨な半生が綴られていた。「太宰治の遺書」とも言われた、日本文学の名作。
日本人なら誰でもタイトルくらいは知っている有名すぎる作品ですが、改めて見てみると強烈なタイトルですよね。「親失格」とか「教師失格」とか失格という言葉ってけっこう使いますが、「人間失格」となると、もはや生きていること、生まれてきたことを否定されるレベル。太宰治が、自殺する一ヶ月前に完成させた、自身の半生を物語として綴った作品にこのタイトルを付けたところが、何とも言えない気持ちになります。タイトルからも分かる通り、暗くて重い作品ですが、それでも作者とともに、今の時代でもファンの多い作品でもあります。それだけ、人の心の不安定な部分や暗い部分を捉えて離さないような、魅力のある作品だと思います。
まとめ
いかがでしたか?
この記事では、私が個人的に秀逸なタイトルだと思う作品を23作、紹介しました。
みなさんにも「このタイトル確かにいいな」「私も好きだな」と思ってもらえたら嬉しいし、実際に読んでみてもハズレのない作品ばかり選んだつもりですので、ぜひ手に取ってみてください。
また、みなさんもぜひ、これから小説を選ぶときや読むときにタイトルにも少しスポットを当ててみて、お気に入りタイトルを見つけてみてください。
では、ここらで。
良い読書ライフを!
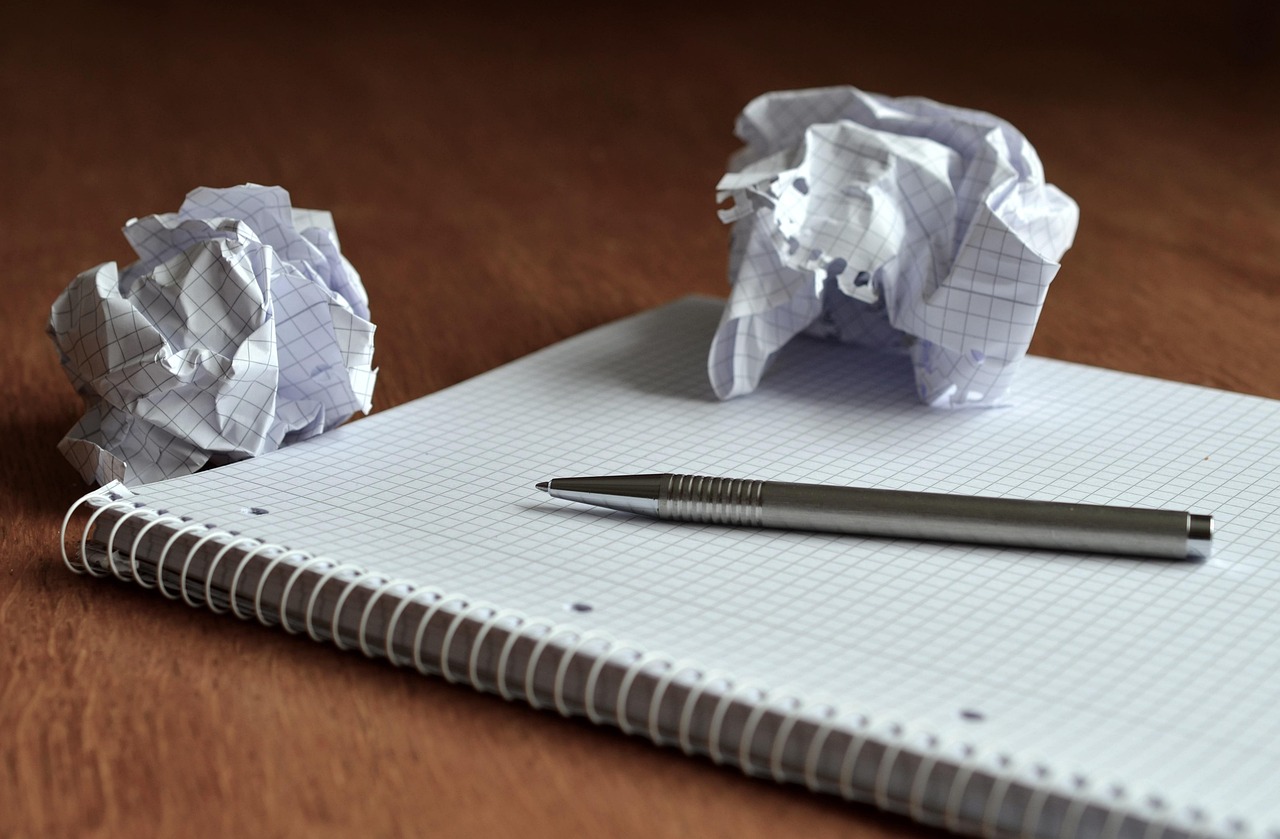


コメント