みなさんこんにちは、らくとです。
小学生の頃からの無類の本好きの私ですが、様々な本のジャンルの中で最も好きなのが「ミステリー」であることは、このブログ内でも何度も書いたと思います。ミステリーマニアの父から本をたくさん譲り受けたことをきっかけに、中学生頃からミステリーを読みあさり始めた私ですが、なぜミステリーというジャンルにこんなにのめり込み、しかも十年近く経った今でもまったく飽きることなくのめり込み続けているのか、ふと不思議に思いました。それはもちろん直感というか、いわば好みである、といってしまえばそれまでですが、せっかくこういうブログという発信の場、思う存分本について語れる場所を設けたのだから、大好きなミステリーについて、その魅力について、考えて、分析して、言語化してみようかな、と思ってこの記事を書くことにしました。
あくまで一人のしがない本好きの考えとして、気楽に読んでいただければ幸いです。
どんなミステリーが面白い?
では早速、どんなミステリーを読者は「面白い」と感じるのか、について考えていきたいと思います。
まず、ミステリーというジャンルを一文で表すと、「作中で何らかの謎が提示され、それを解き明かすことが物語の主軸となっている作品」と言えると思います。
では、ミステリーの評価のポイントは一体どこなのでしょうか。これは本当に人によって様々かと思いますが、個人的な意見として、5つのポイントを挙げたいと思います。その5つとは、「衝撃」「伏線回収」「謎の魅力」「没入感」「完成度」です。一つ一つ、説明していきたいと思います。
衝撃
まず、一つ目は「衝撃」です。文字通り、「いかに読者を驚かせたか・衝撃を与えたか」ということです。
この「衝撃」って、けっこうミステリーでは大事な要素だと思います。特に「新本格ミステリー」が台頭してきて以降は、「いかに読者を驚かせられるか」というところを作家が競っているような、そんな傾向もありますよね。常識外れのトリックが用いられていたり、予想もしなかった真相がいきなり明かされるような作品は、この「衝撃」ポイントが高いといえます。最も分かりやすい例をあげるなら、いわゆるどんでん返しもの。これはほとんど「衝撃」一本で勝負しているといっても過言ではありません。
そもそもミステリーというのは、常に読者に対して挑戦しているジャンルとも言えます。様々なミステリーが世に出ていき、使い古されたともいえるトリックが増えていく中、いかに読者の心に残る作品にするか・・・それを考えたとき、「衝撃」というのはやはり欠かせない要素だと思います。最近ではあの手この手で読者に「衝撃」を与えようという意欲のある作品が多く、個人的にそういう作品は大好きなので、とても嬉しく思います。
伏線回収
二つ目は、「伏線回収」です。
これも、ミステリーには欠かせない要素と言えるでしょう。作中のいたるところに、それとは気付かれぬように張り巡らされていた伏線が、真相が解き明かされるときに一つ一つ回収されていくのは、何とも言えず気持ちがいいですよね。何気なく読んでいたところが、後になって、「あ、これも伏線だったんだ」「ここにもちゃんと意味があったんだ」と分かるのは、ミステリーの醍醐味の一つです。
「伏線回収」というのは、読者を納得させるもので、かつ、よりミステリーを面白く感じさせてくれるものです。いくら意外な真相でも、すごいトリックでも、それが何のヒントもなく、読者のまったく知らないところからいきなり出されても、面白くありません。今まで読んでいたところにちゃんとヒントが隠されていて、読者がそれに気付けるチャンスがあったことが大事なのです。それでこそ読者は驚くこともでき、納得することもでき、そして楽しむことができるのです。
ミステリーに「伏線回収」は付き物であり、一つもないミステリーというのはないと思います。けれど、その中でも特に「伏線回収」に優れている作品というのはあります。無駄なところがほとんどなく、全てが伏線だったり、本当に何気なくささいなことが伏線になっている、など、そういった作品は、作り込みがとても丁寧で、読み終えたときの満足感がすごいです。
謎の魅力
三つ目は、「謎の魅力」です。
「謎」がミステリーに欠かせないのは、言うまでもないと思います。物語の主軸となるのも「謎」ですし、そもそも「謎」がなければミステリーとして成立しません。ということは、解くべき「謎」として用意されているものが面白ければ、当然作品も面白くなるということです。
謎といっても色々ありますよね。犯罪にも繋がらないような些細な謎を解き明かす「日常の謎」というジャンルもありますし、誰かの過去であったり、本心であったりを謎として解き明かす作品もあります。ミステリーにおいて最も多い謎というのはやはり「殺人事件」だと思いますが、それだけとっても、「誰がやったのか」「なぜやったのか」「どうやってやったのか」などで「謎」の種類は様々に分かれてきます。もちろんそれは一つではなく、一つの事件に多くの謎があります。
個人的に、「魅力的な謎」というと真っ先に思い浮かぶのが「密室」です。ミステリーというジャンルが誕生してからずっと長い間多くの作家さんが挑戦してきた「密室」は、現代もなお廃れずに様々な作家さんに挑戦され続けています。それほど魅力的な謎ということだと思います。
没入感
四つ目は「没入感」です。
ミステリーというと、他のジャンルと比べて一気読みしてしまう作品が多い印象を受けます。なぜかというと、ミステリーというジャンル自体が、文章を通して読者に「非日常」を届けるものだということがあると思います。(いわゆる「日常の謎」は例外とします)。事件なんて、実際に身の回りではそうそう起こらないもの。というか、物騒なものなら、起こって欲しくもないものですよね。ミステリーというジャンルは、そういった恐怖やスリルを伴う非日常を、読者という安全な視点から味わうもの。そして、「非日常を味わっている」と読者に思わせるためには、読者を、安全な場所にいながら、いかに物語の世界に入り込ませるかが重要となります。それを、この記事では「没入感」と呼びます。没入感の深いミステリーは、ページをめくる手が止まらず、一気読みしてしまうことも。
では、「没入感」の深いミステリーとは、どういったものでしょうか。それは色々あって、例えば主人公や登場人物たちが何らかの危機的状況にある場合や、山奥の村や絶海の孤島など、舞台設定が特殊な場合。また、最近よく見られる特殊設定もののミステリーなどもあげられます。
完成度の高さ
五つ目は「完成度の高さ」です。
「それって、これまであげた四つを含めた総合点なんじゃないの?」「完成度の高いミステリーが面白いっていうのは当たり前じゃん」と思うかもしれませんが、ここで言う「完成度」というのは、少し消極的な意味も含まれます。いいかえると、「完成度の高さ=マイナスポイントの少なさ」です。
読んでいて、すごく面白いんだけど、どうしても納得いかないところがあるミステリーってけっこうあるんですよね。「ここがなければ完璧なのに!」とか、「このトリック、すごく面白いけど、実際にこんなこと可能なの?」とか、「結末は本当にこれでよかったのかな」とか、もやもやが残るというか。もちろん、多かれ少なかれどの作品にもあるとは思うのですが、やはり少ない作品は、それだけ曇りなく「面白い」といえるのではないでしょうか。
名作で考える
では、実際にミステリーの名作と呼ばれている作品は、この五つの条件がどれほど当てはまっているのでしょうか。名作と呼ばれている以上、面白いミステリーであることは前提として、その作品が特にどのポイントで高く評価されるのか、それを見ていきたいと思います。
ちなみに分かりやすいように、ここからは、作品ごとに、「衝撃」「伏線回収」「謎の魅力」「没入感」「完成度の高さ」、五つのポイントの評価の高さを★の数で表したいと思います。(★は最高で五つとします)
※なお、もちろんこれはあくまで私、らくとの個人的な評価なので、納得できない部分もあると思いますが、「こういう意見もあるんだな」と温かい目で見ていただければ幸いです。
獄門島:横溝正史
まずは、横溝正史の「獄門島」です。
衝撃:★★★
伏線回収:★★
謎の魅力:★★★★
没入感:★★★★★
完成度:★★★★
まず優れているのが没入感。そもそも横溝正史さんの作品自体が、没入感の高いものが多いですよね。村や島に残っている因習とか人間同士の古い繋がりとか、そういったものが絡まった、少し古くさくおどろおどろしい雰囲気が現代の読者を作品世界に引き込みます。また、美しい三姉妹が次々に殺されていったり、その現場に奇妙な手がかりが残されていたりと、謎も不気味で魅力的。まさに正統派ミステリーのお手本であり、金字塔ともいえる作品です。
十角館の殺人:綾辻行人
次は、綾辻行人さんの「十角館の殺人」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★★
これを読んでいないと本格ミステリーは語れない、と言っても過言ではないくらいのレジェンド作品です。最近実写化されたことで、30年以上の時を経て再び話題になっています。
まず、最も優れているのが「衝撃」。これは間違いなく★五つでしょう。あの衝撃は、刊行から30年以上経っても色褪せておらず、そして、これからもずっと語り継がれていくと思います。あれほど簡潔で美しい衝撃というのは、長いミステリーの歴史でもなかなかないと思っています。けれども、「衝撃」だけが注目されがちな本作ですが、その衝撃までの伏線もとても入念に張られていて、「伏線回収」という点でも素晴らしい作品です。そして、島でのクローズドサークルという状況の中で一人また一人と仲間が殺されていくという緊迫感があり、「没入感」にも優れています。
斜め屋敷の犯罪:島田荘司
次は、島田荘司さんの「斜め屋敷の犯罪」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★
謎:★★★
没入感:★★★
完成度:★★★
本格ミステリー界のレジェンド・島田荘司さんの中でも特に有名な作品のうちの一冊です。個人的に大好きな作品なのでここに選ばせていただきました。何が私の心を掴んだかというと、ひとえにそのトリックの素晴らしさ。北海道の外れに建つその名の通り、少し斜めに傾いた屋敷、通称「斜め屋敷」で起こる密室殺人事件の謎を名探偵御手洗潔が解く、という話ですが、私の中では、密室ものの傑作を三つ選べと言われたら、これは必ず入ります。それくらいに衝撃を受けました。
容疑者Xの献身:東野圭吾
次は、東野圭吾さんの「容疑者Xの献身」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★
謎の魅力:★★
没入感:★★
完成度:★★★★★
日本一の人気作家といっても過言ではない東野圭吾さんの代表作のこちら。本格ミステリーといっていいのかどうかは微妙なところですが、ミステリーとしても一つの物語としても素晴らしい作品なので、選びました。注目すべきはその完成度の高さ。事件の始まりから、展開、突如明かされる衝撃の真相、そしてラストシーンまで、全てが美しく完璧な作品でした。
魍魎の匣:京極夏彦
次に紹介するのは、京極夏彦さんの「魍魎の匣」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★★
謎の魅力:★★★★
没入感:★★★★★
完成度:★★★★★
京極夏彦さんの百鬼夜行シリーズの中でも一番有名で、ミステリー界全体でも傑作と評価する人の多い作品です。箱のような奇妙な建物や少女バラバラ殺人事件、少女の列車事故など、様々な謎が複雑に張り巡らされ、そして、最後には綺麗に繋がります。本の分厚さを見ても分かるように、かなり長い物語なのですが、だからこそ、全てが分かった末に辿り着くラストシーンは震えるほど圧巻。戦後数年という時代背景や、使われている文体や漢字・言葉の古めかしさ、そして全体に漂う少し妖しく不気味な雰囲気も、読者を物語に没頭させます。
双頭の悪魔:有栖川有栖
次に紹介するのは、有栖川有栖さんの「双頭の悪魔」です。
衝撃:★★
伏線回収:★★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★★
有栖川有栖さんの「学生アリスシリーズ」の3作目であり、代表作でもある作品です。有栖川有栖さんといえば、トリックよりもロジックを重視するいわゆる論理ミステリーに定評がある方ですよね。本作のような論理ミステリーは、小さな手がかりから一つ一つ可能性を排除しつつ、じわじわと真相に近づいていくので、衝撃は少なめかもしれません。けれども、見落としていた些細なことが手がかりになっていて、そこから思いがけない真相が少しずつ見えてくるのは、とても面白いです。また、本作の舞台は、奥深い山の中にある芸術家たちの村。しかもそこに渡る橋が大雨で断絶されるというクローズド・サークル付きで、没入感もバッチリです。
すべてがFになる:森博嗣
次は、森博嗣さんの「すべてがFになる」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★
謎の魅力:★★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★★★
ミステリー界でもかなり有名な、森博嗣さんのデビュー作です。形容詞一言で言い表すなら「美しい」という言葉がぴったりなミステリーです。作者が工学部教授ということもあり、登場人物の会話や事件の手がかりなども理系に絡んだものが多いのですが、同時に哲学的でもあり、いうならば「理系的哲学」が作品全体を貫いています。この雰囲気に引き込まれる方も多いはず。そして、何よりも美しいのはその謎解き。凡人には到達しえない高度な領域にある真実に、私たちはただ恐れ、驚くしかありません。謎めいたタイトルの意味にもご注目。少し難易度高めのミステリーです。
向日葵の咲かない夏:道尾秀介
次は、道尾秀介さんの「向日葵の咲かない夏」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★
道尾秀介さんの代表作であり、問題作でもある作品です。好き嫌いは分かれるかと思いますが、どちらにしろ、一度読んだら忘れられない作品です。
衝撃については、間違いなく★5でしょう。しかも、今までに経験したことのない類の衝撃です。私は、いったいどういうことなんだ?と一瞬頭が混乱し、意味を理解した後はしばらく呆然としました。かなり気づきにくくはありますが、伏線もしっかり張られていますし、終始漂っている何とも言えず気持ちの悪い異様な雰囲気に、読者も心ごと呑込まれるはず。完成度については、確実に好き嫌いが分かれるだろうということで、少し低めにつけました。
殺戮にいたる病:我孫子武丸
次は、我孫子武丸さんの「殺戮にいたる病」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★
完成度:★★★
こちらもミステリー界の傑作であり同時に問題作でもある作品です。グロや倫理観の欠如した描写などが多いため、好き嫌いは分かれると思いますが、ミステリーとしての面白さに異論がある人はほとんど見かけません。
衝撃は間違いなく★5つ。ほぼ衝撃一本で勝負しているといっても過言ではない作品です。延々と続く目を背けたくなるようなグロ描写や胸くそ悪い描写を耐えた先、最後の最後に、ミステリー界の歴史に残る、どかんと大きな衝撃が一発。二度読もうとはあまり思いませんが、一度は読んでおきたい名作です。
オリエント急行の殺人:アガサ・クリスティー
次に紹介するのは、アガサ・クリスティーの「オリエント急行の殺人」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★
完成度:★★★★
「ミステリーの女王」と呼ばれる世界的ミステリー作家、アガサ・クリスティーの中でも3本の指に入るであろう作品です。何十年もミステリーファンに愛され続けるに値する傑作です。
全体的にかなり正統派のフーダニットという印象でした。奇抜なトリックや騙しを使わずに、ここまで正統に、しかししっかりと衝撃を与えられるのは、さすがミステリーの女王といったところ。起こるのは比較的普通の殺人事件ですが、雪で止まってしまった列車の中という舞台設定が、読者を物語の世界に引き込みます。
Yの悲劇:エラリー・クイーン
次に紹介するのは、エラリー・クイーンの「Yの悲劇」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★
完成度:★★★★
ミステリー好きならタイトルくらいは聞いたことがあるくらい、海外の古典ミステリーでは有名な作品です。ドルリー・レーンという探偵が活躍する4部作の内の2作目に当たります。
事件自体はわりと普通の殺人事件なのですが、衝撃的なのはなんといってもその真相。真相が明かされたとき、そんなことがあるものかと思い、にわかには信じがたい思いがしました。もう何十年も前の作品ですが、何年経っても、この衝撃、そして恐ろしさが色褪せることはないでしょう。そして、エラリー・クイーンの作品だけあって、真相に至るまでの緻密な論理の組み立ては美しく、見事。ミステリー好きなら、一度は読むべき作品です。
幻の女:ウィリアム・アイリッシュ
次は、ウィリアム・アイリッシュの「幻の女」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★
謎の魅力:★★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★★
海外でも有名なミステリー小説です。
妻殺害の容疑を着せられた男が、アリバイの証人である帽子の女を探し求めるという話です。確かに夜を一緒に過ごしたはずなのに、まるで幻だったように見つからない女・・・その女の存在は謎めいており、不気味ですらあります。そして、この事件には、男の死刑執行というタイムリミットがあり、それまでに何としてもその女を見つけなければいけないということもあって、最後の方はハラハラする展開が多く、ページをめくる手が止まりません。また、ミステリーではあるものの、文章表現は詩的で、全体として綺麗にまとまっており、完成度も高い作品です。
三つの棺:ジョン・ディクスン・カー
次は、ジョン・ディクスン・カーの「三つの棺」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★★★
謎の魅力:★★★★
没入感:★★★
完成度:★★★★
カーというと、海外の本格推理小説を語るには欠かせない作家ですよね。そして、この「三つの棺」は、そのカーの中でも、さらに評価が高く、有名な作品です。
ある教授が、密室状態の部屋の中で胸を撃たれて殺される話です。カーというと、本格推理の中でも特に「密室」に定評のある作家ですが、この作品は、その代表作とも言えるでしょう。圧巻だったのは、そのトリック。密室というと、推理小説界では使い古されたというか、もうあらゆるトリックは出尽くした感があるジャンルですが、このトリックは、それら数多の密室トリックとは少し格が違います。そして、またこの作品が推理小説界で有名な理由として、作中に出てくる「密室講義」があります。探偵役のフェル博士による「密室殺人」の分類と分析が語られるこの「密室講義」は、推理小説ファンなら一読しておくべき。そして、その講義によって引き上げられた密室殺人のトリックに対するハードルを、この作品は軽々と超えてきます。
カラスの親指:道尾秀介
次は、道尾秀介さんの「カラスの親指」です。
衝撃:★★★★★
伏線回収:★★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★★
完成度:★★★★
道尾秀介さんのヒット作です。本格ミステリーとはちょっと違うかもしれませんが、個人的に大好きな作品なので入れさせてもらいました。
哀しい過去を持つ詐欺師たちによる、各々の人生を懸けたやり返し大作戦を描いた作品です。一つ言えるのは、本当の本当に面白い。面白い作品というジャンルがあるなら、今まで読んできた作品の中でも1、2を争います。特に最後の方は、気を休められる時間がほとんどなく、目まぐるしく変わる展開、そして立場の逆転に着いていくのに精一杯。最後の最後まで気が抜けず、ページをめくる手が止まらないのに終わるのが惜しい・・・そんな作品です。騙し合いや大逆転劇が好きな人に全力でおすすめしたいです。
屍人荘の殺人:今村昌弘
次は、今村昌弘さんの「屍人荘の殺人」です。
衝撃:★★★★
伏線回収:★★★★
謎の魅力:★★★
没入感:★★★★★
完成度:★★★★
2017年に発売され、その年のミステリランキングを制覇した傑作本格ミステリーです。少し古めのレジェンド的な作品が多かったので、ここらで最近の作品も欲しいなと思って入れてみました。
事件や推理自体はわりと正統派の本格ミステリーという感じですが、この作品の面白いところは、舞台設定。クローズド・サークルものなのですが、その状況の作り方に度肝を抜かれました。突然、あるあり得ない事態が起きて、何が起こっているのか分からないままに、屋敷に閉じ込められる登場人物たち。その混乱も収まらぬうちに起きる殺人事件、そして事件を推理しながら、その異様な状況を打破する方法も考えるという、まさに息もつかせぬ展開は、一気読み必至。クローズド・サークルの作り方は斬新で大胆ですが、その推理は意外と繊細で論理的なのも面白かったです。ところで、肝心の「あり得ない事態」とは一体何なのか・・・それは読んでからのお楽しみです。
まとめ
どうでしたか?
今回は、私の大好きなジャンルである「ミステリー」をテーマに、その面白さについて私なりに分析をしてみました。ここで題材に上げた作品はどれも、「面白いミステリー特集」を組めば多くの人が名前をあげるような、いわゆる「名作」と呼ばれるもので、かつ私も読んだことがあって面白いと思うものをあげたつもりです。
面白さの条件5つも、それぞれの作品の分析も、やはり私個人的なものになってしまうので、納得がいかないところもあるかと思いますが、しがない一読書好きの他愛ない感想だと思って、優しい目で見てくださると幸いです。(でも、やっぱり共感してくれたら一番嬉しいです。)
そして、ここであげた作品をまだ読んでいないという方は、ぜひぜひ手に取ってみてほしいです。読んで損のない作品ばかりあげたつもりなので。
では、ここらで。
良い読書ライフを!
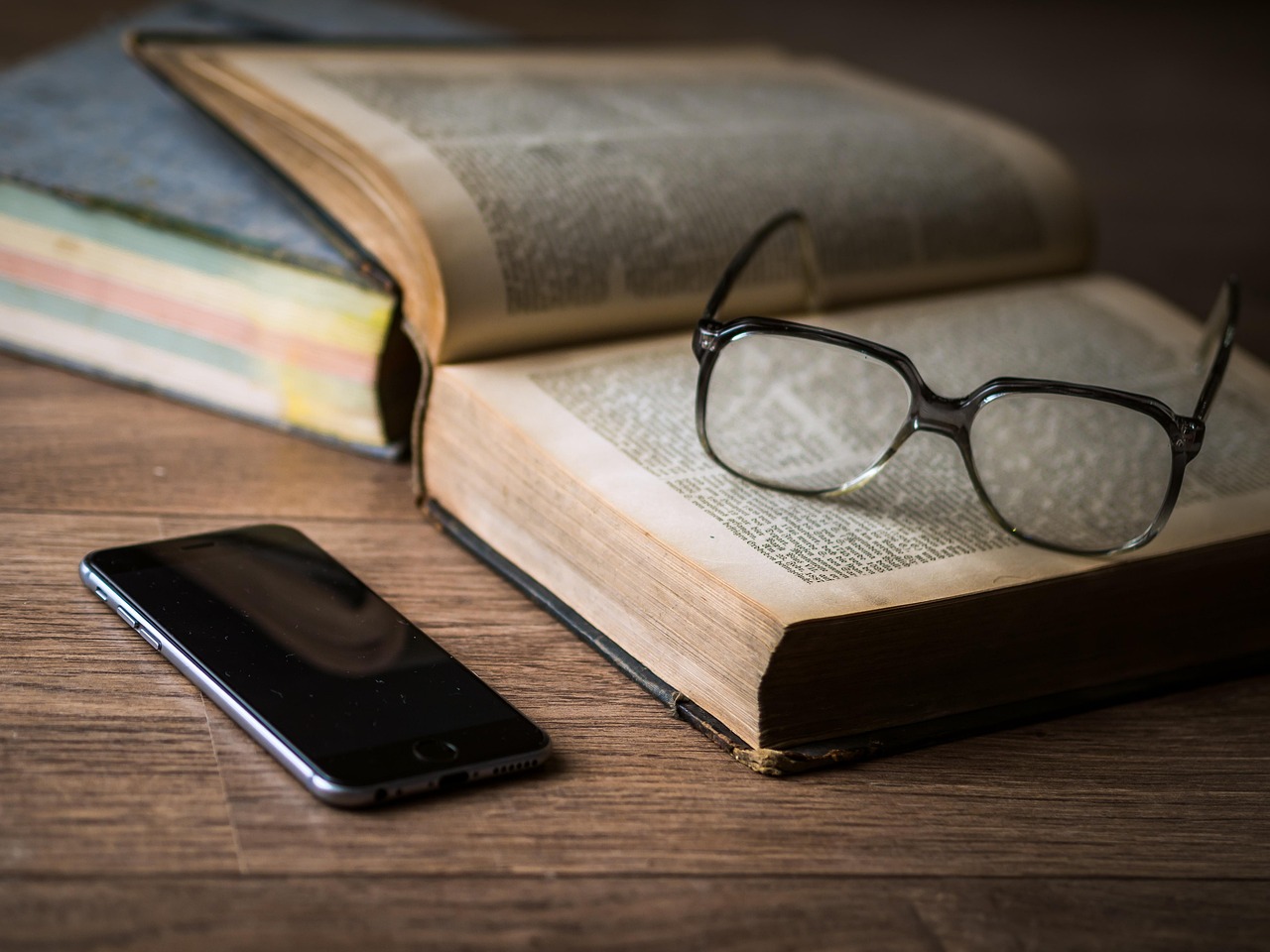


コメント